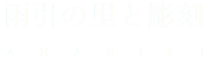ご紹介いただきました藤井匡です。「桜川市市制施⾏ 20 周年記念 ⾬引の⾥と彫刻 2025」の開催おめでとうございます。また、1996 年にはじまったこの展覧会が 30 年を迎えることを重ねてお祝い申し上げます。
実は、この 30 年間の継続というのは、野外彫刻展の歴史のなかでも稀有なことなのです。1961 年にはじまり、2024 年にギネス世界記録に認定された⼭⼝県宇部市は別としますが、1968 年にはじまった神⼾市の彫刻展は 30 周年となる 1998 年に終了します。1969 年にはじまる箱根彫刻の森の展覧会は、途中から会場を美ヶ原⾼原美術館に移しますが、これは開始から 26 年後の 1995 年に終了します。1951 年に東京都主催、⼩野⽥セメント協賛ではじまったセメント彫刻の野外展は 1973 年に終了しますので、やはり 30 年には届いていません。このように考えると、「⾬引の⾥と彫刻」の歴史的重要性が理解できると思います。
もちろん、屋内も含めると、もっと⻑く続いている展覧会はたくさんあります。それは、逆にいえば、野外の場合は継続⾃体が難しいことを意味します。その時々の政治や経済の動きを反映するところが⼤きいからです。⽇本全体が好景気に沸き、⾏政の税収も好調だった1980 年代後半には、「彫刻のあるまちづくり」の名のもとに、多くの都市で野外彫刻展が開催されましたが、その動きは 1990 年代前半に終息します。「⾬引の⾥と彫刻」が運営されてきた期間は、⽇本経済のいわゆる「失われた 30 年」にほぼ重なるのです。先に挙げた野外彫刻展が 1950 年代から 1960 年代という戦後の経済成⻑期にはじまったのとは状況が異なりますので、それが 30 年間続いてきたという意味合いもまた異なるのです。「⾬引の⾥と彫刻」は唯⼀無⼆の「彫刻のあるまちづくり」以降の彫刻展と呼ぶことができるように思います。
この展覧会がはじまった 1990 年代中頃の状況をもう少し考えてみます。この頃、⽇本ではパブリックアートという⾔葉が⼀般化します。実際の事例に即して考えるならば、それらは都市における再開発に関連した動きだったといえます。そのため、「にぎわい」をアピールすることが求められました。それ以前の野外彫刻展では公園が主要な会場になっており、「やすらぎ」や「うるおい」がキーワードだったのとは対照的です。「雨引の⾥と彫刻」はそのどちらとも異なりますので、こうした点も独⾃性と考えることができるでしょう。
さらに視野を広げて考えてみます。1990 年代は東⻄冷戦の終結期にあたり、世界はグローバル資本主義に⼀元化されます。美術の世界でいえば、それに連動する動きがビエンナーレやトリエンナーレと呼ばれる国際展の急増でした。⽇本のパブリックアートもそうした流れのなかの出来事だったのです。国際的なスターアーティストがサーキットのように世界中をまわるなかで、彼らはそれぞれの都市での作品に、固有の価値があることを証明する必要に迫られますが、その際、開催都市の場の固有性が作品の固有性を保証するように語られたりもしました。
「⾬引の⾥と彫刻」が⾏われてきたのはそうした時代だったのです。もちろん、この展覧会でも、それぞれの彫刻家は細⼼の注意を払って設置場所を選んでいますが、その選定理由に⼝実のようなものは必要ありません。もっと素朴に、彫刻作品がどのように⾒えるのかを⼤切にしているのです。
このように作品べースで考えることができたのは、この展覧会が彫刻家の主導で運営されてきたことに由来します。アーティスト主導による野外展はめずらしいものではなく、20世紀後半の⽇本でもさまざまなかたちで実践されました。ただ、それらはそれほど⻑く続くものではなかったのです。では、なぜ「⾬引の⾥と彫刻」では⻑期的な継続が可能だったのか。私はその理由を「彫刻シンポジウムの精神」に求めたいと思います。
彫刻シンポジウムとは複数の彫刻家が寝⾷をともにしながら、同じ場所で作品を制作する企画を指します。本来的には素材の限定はありませんが、制作場所や使⽤機材の都合から⽯を対象とする場合が多く、1959 年にオーストリアではじまったときも、1963 年に⽇本で最初に⾏われたときも⽯を素材としていました。「⾬引の⾥と彫刻」はシンポジウム形式ではありませんが、この地域が⽩御影⽯の産地だということもあり、⽯彫家が多く参加しています。
この彫刻シンポジウムも 1980 年代の「彫刻のあるまちづくり」のなかで多く⾏われたものですが、その動きはやはり 1990 年代にほぼ終息します。しかしながら、その精神は別のところにあります。重要なのは彫刻家主導で運営されること、そして、彫刻家のネットワークを通じて展開されることです。その精神は彫刻家同⼠が制作を通じて相互に助け合うこと、議論を通じて相互に理解し合うことにあるのです。私はこの精神がこの展覧会を持続させてきた最⼤の要因だと考えています。この意味でも「⾬引の⾥と彫刻」を「彫刻のあるまちづくり」以降の彫刻展と呼ぶことができると思います。
とはいえ、その精神が彫刻家のあいだに留まっているだけでは継続は困難なはずです。実際、ここに参加する彫刻家たちは、⾃作の設置場所の交渉などを通じて、その精神を地元の⽅々と共有することを続けてきました。
本⽇より展覧会がはじまります。展覧会を通じて、地元の⽅々、あるいは、⾒に来られる市外の⽅々とそうした精神の共有が進めば素晴らしいと思いますし、そうなることを期待いたします。ご清聴ありがとうございました。
藤井匡