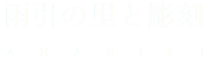学生時代に初めて「雨引の里と彫刻」を訪れた時には、いずれ自分が参加することになるとは思ってもみなかった。それが作家として駆け出しの頃にメンバーとなり、今回で早くも4回目の出品となる。
作家による自主運営を公然とするこの展覧会の舞台裏は、初参加当時の私にとって尋常なものではなかった。月一回の会議で繰り広げられる喧々諤々の真剣なやりとりには、格別の緊張感があった。展覧会開催に関わる全ての物事に向き合い、起こる事態に処していく。解決の道筋に予定調和は持ち込まず、面倒を承知で一から全員で話し合う。その過程で露わになるそれぞれの作家の気質。発せられた言葉の全てが、そのまま自分に返ってくるような抜き差しならない時間。私は渦中にいながらも、そこに社会の縮図を見る思いでいた。
そうした縮図は、作家各々の人生の歩みや社会との関連の中で徐々に有り様を変えて行く。「雨引の里と彫刻」も時の流れと共に、真っ当に変化を遂げて来た。しかし、人ごとではない。ふと自身を顧みればこの縮図の一員である自分の内部に、さらに縮図があることに気付かされる。十人十色の作家達を鏡に、否応なく多様な自己が照らし出される。
社会は分業。人は各々の専門を引き受け、その他を人に委ねることで初めて限られた時間で何事かを成し遂げることができる。展覧会も同様だ。作家と表現に携わるいくつかの職種が役割を分担して効果的に仕立れば足りる。
しかし、「雨引の里と彫刻」はそれをしない。おそらく、作品制作以外の苦労を忘れて常態とするうちに、作り手として失うべきではない何かを取りこぼす可能性を、鋭敏に察知しているからだろう。大変な労力をかけて自覚し続けていることはいったい何か。それは、分業以降の歴史の中で自明となった「美術」という枠組みには求めにくい手応えのようなもの、言葉にするのは難しいが敢えて言えば「確かさ」なのかもしれない。
ひるがえって歴史を眺めれば、これまで多様に展開してきた表現はそれぞれの「確かさ」と共に成し遂げられてきたとも言える。
自明性への問いを掲げたり、枠組みの先端で斬新を狙う際にもそれは伴っただろう。これに対して「雨引の里と彫刻」は、風景の中に作品を置いて人に観せるという極めてシンプルな行いに専心するだけだ。だが、その過程で意義と責任の両方を受け取りながら、結果的に枠組み自体の形成過程を辿るような仕方で、表現における「確かさ」を獲得していく。
ルートを巡り全ての作品を観る。作品は作家、観者、地域、そして社会をお互いに照射させ合う。その錯綜する反射がまた私の内部の縮図と反射する。私は内と外との変化の一時的な事情として佇んでいる。一方、作品はそんな生身の人間の機微とは無縁であるかのように、里山の暮らしの中に当たり前に存在する。それは「確かさ」を伴って観た人の記憶に残るのではないだろうか。そして、時を経る中で想起される度に解釈を更新させるに違いない。作品は思い返され、更新された分だけ作家に、ひいては観者へ新たなヴィジョンを与える。次の一歩を促しながら。
参加作家 塩谷 良太