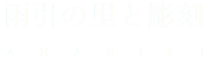今回の展覧会が開催される時期が決定し、作品の設置されるエリアを下見のために訪れたのは、ちょうど1年前のこの時期であった。田んぼには、稲刈り間近の稲穂がたわわに実り、早いところではもう刈り入れが始まっていた。会期はおよそ3ヶ月の長期に渡るため、始まりと終わりの時期では、彫刻を取り巻く風景が一変してしまう。だから作家は、夏のムンムンとする新緑が残る季節から、冬の到来を感じさせる晩秋の頃までを見通さなくてはならない。そして、他の作家とぶつからないように気を配りながら(いや、邪魔されないように、と言った方がいいかも知れない)、これから作る作品に最もふさわしい場所を求めて、あるいは場所からのインスピレーションを感じるために、半年に渡って足しげくこの地を訪れる。
しかしながら、その時点で、誰がどのような作品を持ち込んでくるのかは全くわからないから、自分の作品と全体との関わりを意識してはいない。ちょうど各々の個展会場を見るようなイメージで、設置場所を選んでいく。ところがどうだろう。いざ展覧会が始まってみると、個々人の個性が見事に、このエリア全体を生き物の細胞さながらに機能させ、結実した生命体のように演出しているではないか。「モノ作り」は得てして、他との協調性に乏しい人種と見られがちだが、いやいやどうして、力を合わせて発表することにより、個人にも全体にも良い結果が生まれることに、改めて感動した。
参加作家である私は、「モノ作り」の一人ではあるものの、美術・芸術に見識が深いわけではない。正直なところ、理解に苦しむ作品に出会うこともしばしばである。例えば、裸体像を見る。作品の題名は「女」。大変安心する。意味のあるものは、人を安心へと導くからだ。しかし、それで本当に「解かった」と言えるのだろうか。意図がわかってしまうと面白くなくなることが多々あることも、事実だ。
スタート地点であるシトラスには、作家の一言が記されたチラシが地図と共に用意されている。文章では表現しきれない思いを短いポエムに託したものから、端的に事実を記したものまで多様である。これらを作品と照らし合わせながら、回ってみるのも面白い。
作品に紛れて、道すがら放置されているコンクリートの塊や鉄屑、倒れかけた道標に意味はない。迂闊にもそれらに目を奪われ、あれ!これ誰の作品?いいじゃない!!と思ってしまうことがある。これらも含めて作品と見るのもまた、この展覧会の意外な楽しみ方かも知れない。
私が最初にこの展覧会に参加したのは、1997年に開催された第2回展の時である。それ以降毎回、一貫して作品の搬入・搬出に関わる役目を担わせていただいている。今回も搬入時期の2週間に渡り、自前の4トンユニック車を起動し、各作家の設置場所をぐるぐると走り回った。すでに見知ったルートではあるが、この文章を書くにあたり、新たな目線で展覧会全体を見渡そうと思い立ち、自転車を走らせた。自転車は徒歩と車の中間的な速度であるため、作品間を移動する間にも、小さな変化や見過ごしていたものに気がつく。私は小学生の頃、毎日8キロの道のりを歩いて登下校した。あたりにはちょうど、今回の会場のようなシチュエーションが広がっていた。その道すがら、畑に取り残された巨石や放置されたままの廃車の山、鉄製の何かの部品等が、まるで自然の山川と共存しているように見えたことを今でも記憶している。私が彫刻を作る上での礎は、この幼い頃に見た「理解がつかないもの」によるところが大きいと思われる。
参加作家の大多数は、年齢・キャリアは様々であるものの、彫刻を生業としたいわゆるプロである。試行錯誤して現在に至った作品を、一目見て的確に分析し、理解するのは霊能者でも難しい。いや、ひょっとして作家本人も、完全には理解していないのかも知れない。それならばどうして、他人が理解できようか。理解ではなく、不思議なものを知識で結論づけずに、不思議なまま放置することこそが、正しい彫刻の見方なのかも知れない。
最後に、遠方よりわざわざ足を運んでいただいた方々、様々な面でこの展覧会を支えてくださった地域の方々に、深く御礼申し上げたい。特に、土地を提供してくださった地権者の方々は、空間を共有するという意味において、作品を展示する作家と近い立場にあり、我々一同、感謝の念に絶えない。この「雨引の里と彫刻」は、飽和状態にある美術シーンに、発表する「場」のセクションとしても新しい可能性をもたらすと感じている。
参加作家 松田文平