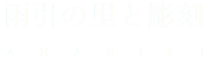雨引の青年たちは何処へ
「雨引の里と彫刻2006」は4月1日の桜の開花の時期と共に始まり、やがて色鮮やかな緑が芽吹き、徐々にその緑を濃くしてゆく梅雨直前の6月4日に終了した。2週間後にはすべての作品は撤去され、雨引の里にはいつもの静かな時間が流れてゆく。
4月から5月という時候の良さや新聞各紙に展覧会の模様が掲載され、またテレビ、ラジオに放送されたこともあり、芳名帳だけでも前回の1.5倍の1500人の名が記されている。会期中のイベントのバスツアーでは、定員を多く上回る参加申し込みがあり、2回目のバスツアーは定員を増やし、更にバスをもう1台増やしたものの、断りを入れる程の盛況ぶりであった。各日曜日にはボランティアによる「大和撫子庵」の休憩所、お茶のサービス、また「手打ち蕎麦大好き会」の蕎麦実演販売もあり、全長約15キロの展覧会コースを回る人々に息継ぎの場を提供してくれた。関連イベントとして4月24日から28日まで東京のギャラリーせいほうで「雨引の里から」と題しプランニング展を開催。44人の作家の作品のプランや小品を展示し、短い期間であったがサテライト・ギャラリーとしての役割を担った。
すべての作品が撤去された現在、この里山に、そして人々にどのようなものを残すことができたのだろうか。44人の参加作家の中にはいまだ冷めやらない熱い何かが残っているようだ。
10年程前、石の産地であるこの地を制作の場とする7人の石彫家により、「第1回 雨引の里と彫刻」は始まった。町や村が主催するのではなく、彫刻家が自主的に運営し、展示場所を自分で探し、地権者の許可を得、その場との対話のなかで制作、設置する形態の展覧会として。このことは展覧会の基盤として現在まで踏襲され、また、展覧会の特徴にもなっている。里山や集落の風景は美しい展示空間としても、また地元の人々、地域社会との関わりといった社会的空間としても、彫刻家を誘発した。美術館、画廊といった空間は、あらかじめ見ることを前提とし、どのような作品であれ、美術として自明のものとして守られる。しかしこの場では、地元の人々との美術に対する認識のギャップから、彫刻家たちの活動は時に奇異に見られ、誤解され、無視されるといった風雨にも曝される。このような体験は、各作家が今一度、自分の作品を振り返り、また美術の在り方を再検討する機会となったのである。各回ごとに参加作家の数が増え、44人の大所帯となった今も、美術や彫刻の存在意義を自分の中で問い直すきっかけとなるものをこの雨引の展覧会は有している。
場所選びからすでに作品制作は始まっている。どのような場を選び、そこに何を読み取り、その場といかなる関係を結ぶのか、それは各作家の目と思考そのものの現れである。同じ場所であっても各作家により、全く違う視座を持つだろう。それは作家どうしのお互いの新たな発見となり、刺激となる。いい意味でのライバル意識がうまれてゆく。多くの団体展、グループ展が年月を経ることで、はじめの理想や緊張感が失われ、形骸化している現在、10年経った今でも、このような意識が失われず、グループ展としての理想の形を保持しているのがこの雨引の展覧会ではないだろうか。それは雨引の里という場が持つ力なのだろうか。あるいは自主運営と言う形で保持された作家の意志、欲望と言い換えてもよいものなのかもしれない。
とはいうものの、多少のほころびと惰性を感じた前回展からの仕切り直しとして今回の展覧会は動き始めた。町村合併により大和村から桜川市への移行も一因であるだろう。展覧会開催の有無、展覧会名称の問題だけで約3回の会議がもたれた。より良い展覧会にしてゆく為に、今までの反省点、問題点をひとつひとつ検討していった。約1年前から、毎月一回定期的に会議は開かれ、必要事項が決定されていく。各作家それぞれが各係に着き、年齢やキャリアなどに関係なくこの展覧会に対し等しい責任と義務を担う。毎月の会議は各作家の気持ちを徐々に高揚させ、連帯を深める儀式であるのかもしれない。このような準備の末、ポスター、案内状の発送を最後に、今回の展覧会は「雨引の里と彫刻2006」と、名称も新たにオープンした。
結果は冒頭で書いたように今までにない成功をもたらした。
場の特性を生かした作品が多く、これまでにない場への作家の目と思考が感じられる力作が多かった。春の爽やかな風の中を自転車で回られた方は、そのことを体感していただいたのではないだろうか。何人かの作家にとっては今後の重要な展開を示す作品になったであろう。
バスツアーは作家のトークもあり、欠かせない人気イベントとなった。
各マスコミの批評も今までの「彫刻家が手弁当で展覧会を実施」という記事から各作品を言及した批評になっている。また「場との関わりが借景的である作品が多く、地域社会との関わり方で物足りない」という批判的な記事もあったのも事実である。
2ヶ月の会期中に、周囲の環境は刻々と変わっていった。5月に入ると田圃には水が張られ風景は一変した。いっせいに農作業の音、蛙の鳴き声が聞こえ始めた。緑は濃くなっていった。環境の変化は作品の見え方や在り方にも微妙な変化をもたらした。野外展示のおもしろさと同時に、改めて日本の風土の中で人々の生活と自然が作り出した里山の美しさや豊かさに目を向けるのであった。
また地元の人の行為が思いもかけず作品空間を変えてしまう出来事もあった。例えば、5月の初め、大和駅舎内に設置されたテーブルの作品の背後に市民ギャラリーと称してパネルが立てられ写真展が開催されてしまったこと。これは以前からの無人駅の環境を改善したいという、行政と地元の人の行為であり、雨引の展覧会をきっかけに行動してしまったことであるが、作家の意図した駅舎の空間の意味が変わってしまい、撤去していただいた。作品に対する理解や認識の溝を埋めることの困難さを感じた出来事であったことを報告しておこう。
展覧会最終日の打ち上げの席で、実行委員長の菅原二郎は今回の成功を讃えながら、次のようなことを語った。「やっと、まともに批評され、また批判される段階にたどりついた。それは10年間の地道な活動がどうにか理解され、根付き始めたからこその批評、批判であり、そのことを真摯に受け止めていく必要があるだろう」と。
その夜、今回の展覧会で起きた幾つかの問題について皆で語り合った。展覧会の成功とは裏腹に各作家の展覧会への関わりの温度差、桜川市との関わり、メール連絡よる作家間の意志の疎通の問題、地元の人々との美術に対する考えのずれから起きる様々な問題について。かなり酒も入っていたが。
この展覧会の持つ純粋さや熱さは青年期特有のものに感じられる。
雨引における各作家の愚直なまでの作品や展覧会への取り組みは、きわめて個人的な表現欲に支えられている。今、その個人、個人の営みの集合が地域社会において無視できない文化活動になりつつある。
青年期から次の段階へ成長してゆくその起点に僕たちはたたされた。
個人の表現と社会との関わりの中で、僕たちはどのような方向に向かうのか、また何回も語り合うことになるだろう。
参加作家 金沢健一