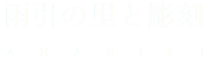彫刻の周辺
何度訪れてもこの里山の風景は美しい。春夏秋冬、その何れもがそれぞれに良い。「雨引の里と彫刻」の作家達の情熱を支えているのはまずはこの風景に違いない。林間を歩いて行くと、少しずつその姿が現れてくる作品。畦道で遠くからだんだんと近づいてくる彫刻。また、道を曲がると突然とあらわれるもの。様々なかたちで点在する作品たちがこの里山の中にある。
参加作家は1年以上もまえから何度もこの地に足を運び、作品の居場所を探すわけですが、これがなかなか楽しくもあり、また難しい。広い里山の中で自分の作品の居場所を決めるということは、それ自体既に作品の制作が始まっているのと同じことです。設置場所のみならず、作品に出会う道程などもそのまま作品をとりまく空間へのエピローグとなっていきます。作家には広い意味での空間の意識、空気感のようなものが要求されているわけです。多くの作品が設置されている、飾られているというより存在しているという感が強いのは、個々の作家達の空間への深いこだわりの表れといえるのでしょう。
「雨引の里と彫刻」の最大の特徴はなんといっても自主運営ということに尽きます。この自主運営というものが大変で、作家にとっては非情なまでの負担ともなります。しかし、その自主運営の‘大変さ’と引き換えに我々の得ているものは大きい。自分あるいは自分達で全てを決めて展覧会を催すということは、これはもう作家にとって裸身をさらしているようなものです。裸身になり自分の思いを作品という形で表現できる環境は少なく、作家はどこかでそれを求めているからこその‘大変さ’なのです。
また、今回の「雨引の里と彫刻」が前回までと大きく異なる点は、茨城県の国民文化祭に参加するという形で行われたことです。自主運営というシンプルな形で続いてきた展覧会が、そのシンプルさを損なうのではないかと作家たちは随分と不安を覚えたものです。参加か不参加か、月一度の話し合いは数ヶ月にも及びました。
民俗学者の宮本常一の著「忘れられた日本人」の中に昔の農村での‘寄り合い’での様子が著されています。その場景が「雨引の里と彫刻」の在りかたと酷似しており、苦笑をまた禁じえません。昔の農村では、ちょっとした取り決めをするのにも村人全員が納得のゆくまで延々と話し合いを続け、時には夜を徹して何日もそれが続くことがあったそうです。
「雨引の里と彫刻」もまた「忘れられた日本人」のように時間をかけ、これからもゆっくりとその歩を進めていくことになるでしょう。
参加作家 山﨑隆